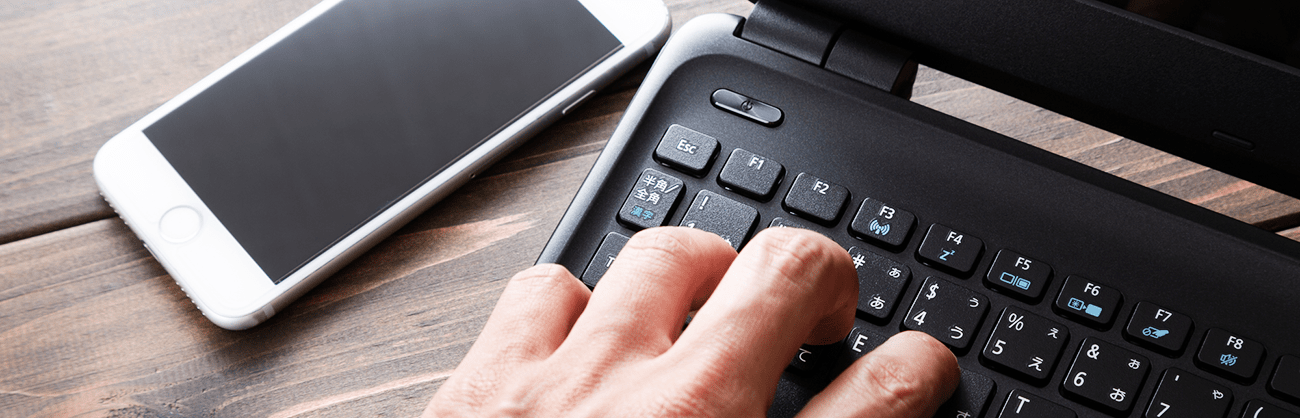固定電話の安心感をスマートフォンの気軽さで
- 固定電話の発着信をスマホで操作できるサービスを比較!
- > コラム一覧
- > なぜスマホは災害時に使えない?情報収集・安否確認・救援要請の方法
なぜスマホは災害時に使えない?情報収集・安否確認・救援要請の方法

「スマホ=防災グッズ」と認知されている理由は、災害時の安否確認・救助要請・情報収集などに欠かせないツールだからです。
とはいえ、地震や津波が発生した直後は誰もが冷静さを保っていられないでしょう。
そこで今回はなぜ災害時にスマホが使えないのか、その原因を踏まえたうえで不安定な通信環境下で効率的にスマホを活用する方法についてご紹介していきます。
携帯キャリアのインターネット通信がダウンした時の対処法や、政府が推奨しているICTについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
過去の災害に学ぶ!携帯電話のサービス障害
現代におけるスマホは、ライフラインの一部と言っても過言ではありません。
とくに地震や台風といった災害時には、情報収集や安否確認などを行うために欠かせない必須ツールです。
しかし、もっともスマホが必要とされる災害時にもかかわらず、実際には携帯網が使えないことが多々あります。
以下は、スマホが一時的に使えない状態に陥った巨大災害の一例です。
| 時期 | 災害名 | スマホ障害の内容 | 主な原因 |
| 2011年3月 | 東日本大震災 | 約2.9万の基地局が停止し、復旧に1ヶ月以上かかった | ・通信が集中する「輻輳」 ・通信ケーブル切断 ・停電 |
| 2016年4月 | 熊本地震 | 大手3社の基地局が約10%停波したが、翌日にはほぼ復旧した | ・停電 ・通信ケーブル切断 |
| 2018年6月 | 大阪北部地震 | 4.5時間ほど繋がりにくくなった | ・輻輳 |
| 2018年9月 | 北海道胆振東部地震 | 一部エリアで長期間の不通が続いた | ・停電 |
| 2019年10月 | 令和元年東日本台風 | 通話、通信し難い状況が4日間ほど続いた | ・停電 ・伝送路の支障 |
2011年3月の東日本大震災では1ヶ月以上、2019年10月の令和元年東日本台風では数日間にわたってスマホが使えない状態が続き、現状の把握さえままならない被災者は混乱を極めました。
なぜスマホは災害時に使えない?
なぜ災害が発生するとスマホが使えない状態に陥るのか、その主な原因は以下の3つです。
- アクセス集中による「輻輳」
- ケーブル切断などの物理的障害
- 停電で基地局が作動していない
なお、スマホの充電を長持ちさせるコツにつにては、以下の記事で詳しく解説しております。
▼関連記事
アクセス集中による「輻輳」
災害時は大勢の人が一斉に以下のような行動を取るため、スマホの通信回線が一時的にパンク状態に陥り、最悪の場合システム自体がダウンしてしまいます。
- 家族や友人などの安否確認
- 災害情報へのアクセス
- 110や119への救援要請
この状態を通信業界の専門用語で「輻輳(ふくそう)」と言い、110や119といった緊急通信も繋がらなくなってしまうのです。
事実、総務省が公開している「東日本大震災における情報通信の状況」によると、携帯電話の音声通話についてNTTドコモでは平時に比べて50~60 倍ものトラヒック(送受信される信号やデータの量や密度)が発生していました。
そこでスマホの3大キャリアでは緊急通信の不通を解消すべく、音声通話に対して以下のような「接続制限」をかけたそうです。
- NTTドコモ:90%
- KDDI:95%
- ソフトバンク:70%
一方、メール(パケット)におけるアクセス集中は音声通話よりも深刻ではなかったため、NTTドコモのみが30%の通信規制を実施したものの、規制はすぐに解除されました。
ケーブル切断などの物理的障害
災害時にスマホが使えない2つめの原因は、「物理的障害」です。
具体的には以下のよう事例があり、東日本大震災では「太平洋沿岸部の基地局」が物理的ダメージを負い、スマホによる通話・通信が使えない状態に陥りました。
- 基地局とデータセンターを結ぶ光ファイバーが切断される
- 基地局が置かれているビルが崩壊する
停電で基地局が作動していない
災害時にスマホが使えない3つめの要因は、もっとも広範囲に影響する「停電」です。
実際、北海道胆振東部地震では停電の復旧が遅れたため、スマホが長期間にわたって使えませんでした。
地震の影響で発電所の機能が停止する、あるいは電線や電源ケーブルが切断されるとスマホ基地局の機能が停止状態に陥るのはもちろん、稼働している基地局の数が減るほど電波が繋がりにくくなるのです。
それでもスマホは身近な防災グッズ
災害に見舞われる機会が多い日本人にとって、スマホは最も身近な「防災グッズ」と言っても過言ではありません。
通信さえ復旧すれば、たった1台のスマホで以下のすべてを行うことができます。
▼災害時にスマホでできること
- 安否確認
- 救援要請
- 情報収集
これだけ災害時に役に立つのですから、自身はもちろん家族や友人など大切な人達を守ってくれる防災グッズとして、重宝されているのも当然でしょう。
災害時のスマホ活用法①:安否確認の方法
この章では、スマホで安否確認を行う6つの方法についてご紹介していきます。
- 災害用伝言ダイヤル(171)
- スマホキャリアの災害用伝言版
- Google「パーソンファインダー」
- LINEの安否確認
- LINEの位置情報送信機能
- Facebookの災害支援ハブ
では早速、順番に見ていきましょう。
災害用伝言ダイヤル(171)
「災害用伝言ダイヤル(171)」とは、NTTグループが提供・運営している安否確認サービスです。
安否を知らせたい人はメッセージの録音を、安否が知りたい人はメッセージを再生できる仕組みになっており、「阪神・淡路大震災」の教訓を基に開発されました。
「災害用伝言ダイヤル(171)」は誰もが無料で利用でき、以下の通り使い方も非常にシンプルになっています。
▼災害用伝言ダイヤルに録音する方法
- 「171」に電話をかける
- ガイダンスに従って、録音の「1」を入力
- 電話番号を市外局番から入力する(携帯番号でも可)
- 数字の「1」を入力
- 「無事です」「○○にいます」などのメッセージを残す
- 「9」を入力して録音完了
▼災害用伝言ダイヤルを再生する方法
- 「171」に電話をかける
- ガイダンスに従って、再生の「2」を入力
- 相手の電話番号を入力する
- 数字の「1」を入力
- 録音されたメッセージが流れる
スマホキャリアの災害用伝言版
ここからは、4大キャリアそれぞれが提供している災害用伝言板サービスについてご紹介します。
- NTTドコモ
- KDDI(au)
- ソフトバンク/ワイモバイル
- 楽天モバイル
手動操作だけで完了するため、災害用伝言ダイヤル(171)のように通話する必要はありません。
なお、4大キャリアが提供している災害用伝言板サービスは、いずれも震度6などの大きな災害時にのみ利用できる仕組みになっており、平時に使うことは基本的にできません。
NTTドコモ
NTTドコモが提供している災害用伝言板サービスの使い方は、以下の通りです。
▼メッセージの登録方法
- スマホ内の「災害用キットアプリ」を起動
- 「災害用伝言板(通常版)」または「災害用伝言板(簡易版)」のどちらかをタップ
- 「安否の登録」をタップ
- 登録したメッセージをグループメンバーに通知するか設定する(初回登録時のみ)
- 現在の状況に該当する選択肢を選ぶ、もしくは100文字以内(任意)でコメントを入力し、「登録」をタップ
- 登録完了
- 登録お知らせメールを送信する場合は、「送信」をタップ
▼メッセージの確認方法
- スマホ内の災害用キットアプリをタップ
- 災害用伝言板(通常版)災害用伝言板(簡易版)のどちらかをタップ
- 安否の確認をタップ
- 安否確認したい方の携帯電話番号を入力し、検索をタップ
- メッセージが登録されていれば、状態とコメントの確認が可能
- メッセージが登録されていなければ、登録を依頼可能なため「依頼する」をタップ
- 依頼完了
KDDI(au)
KDDI(au)が提供している災害用伝言板サービスの使い方は、以下の通りです。
▼メッセージの登録方法
- 「+メッセージ公式アカウントau災害対策」から「災害用伝言板」を選択
- 災害用伝言板のメニューから「登録」をタップ
- 被災状況を選択肢の中から選ぶ、または100文字以内で任意のコメントを入力して「内容確認」をタップ
- 内容確認後、「はい」をタップすれば登録完了(訂正したい場合は「いいえ」をタップ)
▼メッセージの確認方法
- 「+メッセージ公式アカウントau災害対策」から「災害用伝言板」を選択
- 災害用伝言板のメニューから「確認」をタップ
- 安否情報を確認したい方の携帯電話番号を入力し、「検索」をタップ
- 確認したい安否情報をタップ
- 安否情報が表示される
ソフトバンク/ワイモバイル
ソフトバンクおよびワイモバイルが提供している災害用伝言板サービスを利用するには、専用アプリをダウンロードしなければなりません。
災害時に限られたスマホの充電を無駄に消費しなくて済むよう、事前にダウンロードしておきましょう。
具体的な使い方の手順は、以下の通りです。
▼メッセージの登録方法
- 「災害用伝言板」アプリのダウンロード
- 「災害用伝言板」アプリを開く
- 「登録」をタップする
- 状態を選択肢の中から選ぶ、または任意のコメントを入力して「登録」をタップ
▼メッセージの確認方法
- 「災害用伝言板」アプリのダウンロード
- 「災害用伝言板」アプリを開く
- 「確認」をタップする
- 安否を確認したい相手の電話番号を入力する
- 安否情報を確認する
楽天モバイル
楽天モバイルが提供している災害用伝言板サービスの使い方は、以下の通りです。
▼メッセージの登録方法
- 災害用伝言板にアクセスする
- 「安否の登録」をタップする
- 楽天モバイルの契約者IDでログインする
- 電話番号を選択する
- 安否情報と伝言を入力する
- 「登録する」をタップする
▼メッセージの確認方法
- 災害用伝言板にアクセスする
- 「安否の確認」をタップする
- 安否情報を確認したい方の電話番号を入力する
- 「検索」をタップする
- 確認したい日時の伝言を選択する
Google「パーソンファインダー」
Google「パーソンファインダー」とは、オンライン上で安否情報の提供・確認が行える無料サービスです。
災害が発生した時にだけ提供されるGoogle「パーソンファインダー」、基本的に以下の3ステップで使いこなせるため、防災訓練に組み込んでいる小学校も増えています。
- ブラウザから検索して「パーソンファインダーの公式ページ」にアクセス
- 表示されている「人を探している」、または「安否情報を提供する」を選択
- 相手の氏名を検索、または自分の氏名を登録する
携帯電話番号はもちろん、たとえ名前の漢字表記が分からなくても「ひらがな」で登録・検索ができるため、被災して身動きがとれない第三者の安否情報を、代行して登録することも可能です。
LINEの安否確認
日本で最も利用率が高いLINEでも、災害時に安否確認ができるサービスが提供されています。
最大の強みは、震度6以上の大規模災害時になると赤枠の「LINE安否確認」が自動的に表示され、ユーザーのアクションを促してくれるところでしょう。
LINEの安否確認の使い方は簡単3ステップになっており、初めてでも迷わず操作することができます。
- ホーム画面上部の「安否確認」バナーから「安否を報告」を選択
- 「無事」または「被害あり」を選択
- メッセージを入力して「公開」を選択
LINEの位置情報送信機能
混乱している災害時に自分が今いる場所を知らせたいときは、LINEの「位置情報送信機能」が便利です。
ただし、以下の通りLINEに対し位置情報の権限を許可しなければ使用できません。
▼現在地を送信する方法
- 設定アプリの「アプリ」から「LINE」を選択
- 「位置情報」の権限を許可する
- トーク画面の「+」マークから 「位置情報」を選択
- 表示された地図上に現在地がピン表示されたら、「送信」をタップ
Facebookの災害支援ハブ
Facebookが提供している「災害支援ハブ」は、プロフィールに登録しておいた居住地または現在地が「被災地域」だった場合、自動的に安否確認の通知が届く仕組みになっています。
使い方は、届いた通知に返信するだけの簡単2ステップです。
▼Facebookの災害支援ハブの使い方
- Facebookから安否を確認する通知が届く
- 「自分の無事を報告」または「影響を受けた地域にはいません」を選択
災害時のスマホ活用法②:救援要請の方法
災害時に救援を要請する最も迅速な手段は、消防(119番)や警察(110番)への連絡です。
とはいえ災害時のパニック状態では、日頃から使い慣れているSNSの方をとっさに思い浮かべる人も多いでしょう。
そこでこの章では、各種SNSの中でもとくに拡散力に優れているTwitterで救援要請をツイートする方法についてご紹介します。
Twitter(現X)の救援要請ツイート
拡散力が高いTwitterは、災害時の救援要請ツールとして非常に有効です。
なぜなら、消防署や警察などが災害時の救助活動の一環としてTwitter上で「#救助」を検索しているから。
実際の災害時ではツイートを見た人からの情報提供によって、レスキュー隊が駆けつけて救助された事例も少なくありません。
ただし、救援要請ツイートを送信する際は、できる限り「Twitterライフライン」が推奨している以下のルールに沿って行いましょう。
▼救援要請ツイートの手引き
- ハッシュタグ「#救助」をつける
- 具体的な救援内容を書く(いつどこで、何が起きて、何に困っているのか)
- 写真を添えて、状況を伝える
- 具体的な住所
- 住所がわからない場合は、「位置情報」をつける
上記の項目が満たされているほど救助が早まります。
災害時のスマホ活用法③:情報収集の方法
この章では、災害時にスマホを使って情報収集する方法をご紹介していきます。
- #減災リポートwithウェザーニュース
- 災害時に役立つTwitterアカウント8選
- オフラインでも使える防災アプリ2選
- インターネットラジオ3選
では順番に見ていきましょう。
#減災リポートwithウェザーニュース
「#減災リポートwithウェザーニュース」とは、最新の被災情報がリアルタイムで確認できる「ユーザー参加型」のTwitterアカウントです。
運営はTwitter Japan株式会社と株式会社ウェザーニュースが共同で行っていますが、以下の仕組みによって常に最新の被災情報がリアルタイムで更新されます。
- ユーザーが「#減災リポート」のハッシュタグを付けて被災情報をツイートする
- 寄せられたツイートを元に、位置情報と被災情報がマップ上にプロットされる
災害時には河川の氾濫や土砂崩れなどが発生しがちですが、「いつ・どこで・何が起きているのか」が一目で分かれば安全なルートが確保できるため、二次被害を防ぐことができます。
災害時に役立つTwitterアカウント8選
総務省防衛庁や国土交通省などは、災害情報に特化したTwitter公式アカウントを開設しています。
災害時の情報収集がスムーズに行えるよう、以下のようなTwitterアカウントをフォローしておきましょう。
- Twitterライフライン:@TwitterLifeline
- 内閣府防災:@CAO_BOUSAI
- 首相官邸(災害・危機管理情報):@Kantei_Saigai
- 総務省消防庁:@FDMA_JAPAN
- 国土交通省:@MLIT_JAPAN
- NHK生活・防災:@nhk_seikatsu
- ウェザーニュース:@wni_jp
- 東京都防災:@tokyo_bousai
Twitterライフラインでは、47都道府県別に「災害時に使えるアカウントリスト」を提供していますので、ローカル情報の収集に適しています。
また、現地の災害情報を素早く入手するには、最寄りの自治体や報道機関などが開設しているTwitterアカウントもおすすめです。
オフラインでも使える防災アプリ2選
この章では、インターネットがダウンしていてもオフラインで一部の機能が使用できる防災アプリを2つご紹介します。
- 約13万件の避難場所データベーズを元に、現在地から最も近い施設までのナビが表示される
- 地図機能はオフラインでも使用可
- 緊急地震速報・警報・避難勧告・雨雲レーダーなど、現在地と3つの地域をまとめて確認できる
- オフラインでハザードマップが使用できる防災モードあり
ちなみに、goo防災アプリは地図機能がオフラインでも使用できるため好評でしたが、2023年3月31日付けでサービスの提供が終了しています。
インターネットラジオ3選
災害時にテレビが視聴できなくなった場合におすすめしたいのが、スマホで聞ける「インターネットラジオ」での情報収集です。
国内向けの主なインターネットラジオには以下の3種類があり、いずれも「通常の電波」と「インターネット」を使って同時配信されています。
- Radiko(ラジコ):NHKラジオ第1/NHK-FM/コミュニティFM以外の民間放送
- らじる★らじる:NHKのAM・FM
- コミュニティFM局による独自配信:ローカルニュース
災害時のインターネットに関する調査結果
高速光回線サービス「NURO(ニューロ) 光」を提供しているソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は、「防災の日」にあたる2023年9月1日に合わせて「災害時のインターネット」についてオンライン調査を実施しました。
その結果、全体の約9割の方が災害時にインターネットがつながらない状態に陥るリスクに対し、以下のように回答していました。
- とても不安を感じると思う
- やや不安を感じると思う
不安を感じる理由として多かったのは、以下のような意見でした。
- 家族や知人、同僚の安否確認ができない
- 災害状況がわからない
- 世の中の状況がわからない
上記の調査結果から、多くの方が「インターネットのダウン=人や情報とのつながりが制限される」、と認識していることが分かります。
無料Wi-Fi「00000JAPAN」の使い方
00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)とは、災害時に被災地で無料開放される「公衆無線LANサービス」です。
どの通信キャリアであろうとWi-Fi接続が可能な機種であれば、外国人観光客を含むすべての被災者が自由にアクセスできる仕組みになっています。
「00000JAPAN」の使い方は以下の通りです。
- スマホやパソコンの設定画面で「Wi-Fi」をONにする
- ネットワーク選択の画面で「00000JAPAN」を選択する
ただし、「00000JAPAN」は大規模災害時にIDやパスワードなどを入力しなくても使えるよう、何より「利便性」と「公共性」を優先しています。
暗号化通信などのセキュリティ面は考慮されていないため、あくまで緊急時の「安否確認」や「情報収集」などに限定して使用するのが鉄則です。
災害発生時に重要なICTとは?
ICT(Information and Communication Technology)とは、迅速かつ正確な情報伝達に欠かせない情報通信技術の一種です。
政府は医療・教育・サイバーセキュリティなどさまざまな分野でICTの活用を推奨しており、防災・減災の分野においては以下の項目が4本柱になっています。
- 緊急速報
- 安否確認
- 被害予測
- 情報収集
たとえば、Jアラート(全国瞬時警報システム)やLアラート(災害情報共有システム)も、防災・減災の分野におけるICTの活用事例です。
まとめ
この記事ではなぜ災害時にはスマホが使えない状態に陥るのか、その原因と不安定な通信環境下で効率的にスマホを活用する方法について解説してきました。
スマホは安否確認・救援要請・情報収集のすべてにおいて、被災者をサポートしてくれる優秀な防災グッズです。
ほかにも、アラーム音を鳴らしてレスキュー隊に自分の居場所を伝える、あるいは停電中の懐中電灯としても活躍してくれます。
本記事でご紹介したスマホ活用術を参考に、あらかじめ災害への備えを万全にしておきましょう。